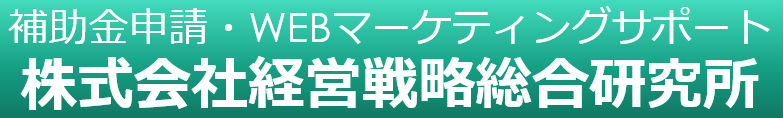中小企業診断士である弊社社長が、日々の活動の中で感じたことを徒然と書いております。
日頃の話題作り、事業の振り返りにつながることがあれば、これ幸いに存じます。
年始ご挨拶・中小企業庁長官年頭所感を受けて(2026年1月4日)
新年あけましておめでとうございます。四国地方では、年末年始、おおむね好天に恵まれ、穏やかな年越し及び年明けとなっています。曜日の配列の関係から、9連休という超長期休暇だった方もいらっしゃったのではないでしょうか。一方で、サービス、小売業界などの方は、一番の稼ぎ時ですので、お忙しい年末年始をお過ごしだった方もいらっしゃると思います。様々な年末年始の過ごし方があるかと思いますが、皆様にとって、今年一年、穏やかで実りある年となりますよう、心より祈念いたします。
さて、毎年元日に中小企業庁ホームページで発表される「中小企業庁長官年頭所感」を見ますと、その年の補助金を中心とした中小企業政策の方向性や狙いが見えてきます。これをチェックして、念頭に置いているかどうかで、政策活用度(補助金採択)に大きな差が生まれると言っても過言ではないでしょう。自社事業の方向性を考えるうえでも、大いに参考になります。
【R8年元旦中小企業庁長官年頭所感】https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/nentouShokan/2026year.html
これだけ読んでいると、なんだいつもと変わらないじゃないか、と思うのですが、昨年の年頭所感と今年のそれとの変化を捉えると、より政策の方向性が明確になりますので、ちょっとやってみたいと思います。
・人手不足の位置づけ
【R7年】一時的・経営上の課題 →【R8年】「労働供給制約社会」という構造問題として明確化
・支援のフェーズ
【R7年】方針・方向性の提示 →【R8年】制度実装・運用段階(改正法施行、具体支援の推進)
・支援対象の広がり
【R7年】取引適正化・生産性・成長投資が中心 →【R8年】これらに加え、事業承継・M&A・金融など事業環境整備を明確に重視
・価格転嫁の扱い
【R7年】重要課題として言及 →【R8年】法制度を伴う実効性重視(取引適正化の強化)
・成長政策(100億企業)
【R7年】ビジョン提示 →【R8年】進捗・成果を踏まえた次段階の支援
・災害対応
【R7年】個別災害対応 →【R8年】継続的・常設的支援姿勢を強調
以上から、今年、補助金申請において留意すべき3点をピックアップしてみたいと思います。
①制度運用フェーズを意識する
R8年版は、政策が制度として具体化・運用段階に移行していることを強調しています。
→ 補助金申請でも「制度の根拠・後方施策との整合性」「施行された法律に基づく取組」を具体化すると評価に資する可能性が高まります。
②事業承継・M&Aや金融環境の記述を強化
R8年版では制度環境整備面の強化が明示されているため、これらも事業計画に入れると政策整合性が高まります。
③長期構造変化(人手不足・人口減)を計画に反映
R8年版は「構造的制約」という言葉を使っています。単年度の課題だけでなく、人口減少・労働供給制約への対応策を計画に加えることで説得力が増します。
補助金は国・自治体の政策実現の手段です。より政策実現に近い申請案件が採択されるのは、補助金の世界の普遍的な事実です。
いまや補助金審査は、人からAIに移行しつつあります。人による目線のブレや偏りがなくなり、AIによる公平な目線(アルゴリズム)で検証・評価されるようになってくるなら、政策の重点を意識した事業計画が採択されやすくなることは間違いないでしょう。
そうした中、少なくとも今後5年間は、国の「省力化投資促進プラン」に沿って補助金予算は維持拡充の方向です。いまや中小企業政策の主軸となった補助金を有効活用することは、競争を勝ち抜くための必須条件といえるでしょう。
弊社は、自治体で、補助金を中心とした中小企業政策の在り方を徹底的に研究し、制度創設・運営していた専門家による、他社にない視座を持った支援サービスを提供しています。補助金を有効活用し、初期投資の軽減や経営効率の上昇といった財務改善効果を享受するとともに、経営課題の解決を図りたいと考える事業者の方は、ぜひ一度ご相談ください。
暑中お見舞い申し上げます2(2025年8月22日)
早いもので8月も下旬に差し掛かりました。あまりにも暑いので暑中お見舞いの第2弾を書きたくなりました。
ここ何日か車のメンテをDIYでしていたのですが、熱中症気味でダウンしておりました。残暑厳しすぎますので、皆様、どうかご無理せずにご自愛くださいませ。
さて、最近、週1日なのですが、高松中心部から徳島中心部まで、片道1時間、往復2時間の自動車通勤が始まりました。讃岐平野のおにぎり山、瀬戸内の多島美、雄大な吉野川と、非常に景色の良い通勤路で、よそ見しないように自制するのが大変です。毎回、新たな発見もあり、四国の良さを改めて実感しています。
また、2時間の間、車を無心で運転していると、いろんなアイデアが思い浮かんできます。お風呂に入っているときに、いろんなアイデアが浮かぶという人は多いですが、私は散歩中と運転中です。
こういった何気なく浮かんでくるアイデアですが、時間が少したつと忘れてしまい、折角、絶妙なアイデアが浮かんでたのに、と自分の致命的な記憶力のなさを悔やみ、本当に何だったんだろうと気になってしまう、というのが、日常あるあるなのは、私だけでしょうか。
とある雑誌で、ファーストクラスとビジネスクラスの乗客で違う点という、キャビンアテンダントの話をもとに、記事にしているのを見たことがあります。その1つの点に、ファーストクラスの乗客は、常に何か(手帳やメモ用紙でしょう。いまならスマホのメモアプリとかでしょうか)に、何かをメモしているそうです。一流の人は凄い才能を持っている人、ではなく、一瞬のインスピレーションを面倒くさがらずにメモし、いつでもリマインドできるようにするという、何気ない行動が習慣としてとれる人なのでしょう。一流とそれ以外の分かれ道なんて、案外そのようなものかもしれませんね。
先週の日経記事から(2025年8月1日)
JR6社のお盆予約1%増 東海道新幹線に「大阪万博効果」2025年7月25日 16:38
JR旅客6社は25日、お盆期間(8月8〜17日)の新幹線・在来線の指定席の予約席数が、24日時点で前年比1%増の360万席だったと発表した。昨年より日並びが悪いなか、インバウンド(訪日外国人)需要が堅調だという。東海道新幹線を運行するJR東海は「大阪・関西万博に向かう乗客もいる」と万博効果があったとみている。各社は予約可能な席数を1146万席と前年に比べて1%増やした。混雑のピークは下りが9日、上りは17日となると見込む。(中略)JR東海の東海道新幹線は2%減の158万席で、JR西日本の新幹線は3%減の102万席だった。両社ともに「前年並みの水準だ」としている。
ーーーーーー
早いもので8月に入りました。8月といえばお盆休み、というのは一昔前。お盆に仕事があって、特に普段と変わらないという方は増えているのではないのでしょうか。大企業勤務、製造業など一部業種の方などは、お盆にまとまった休暇があるのかもしれません。公務員も一緒ではないか、と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、私も地方公務員時代がありまして、お盆休みでなく、夏季又は特別休暇であり、6~9月に5日間付与され、個人の裁量で取得する制度になっています。地方公務員はもともと地元出身者が多く、業務多忙でなく、かつあまり地元から動かない方は、それが良いかもしれません。しかし、地元出身者でなく帰省があったり、地元出身者であっても長期で旅行に行きたい場合で、かつ業務多忙だと、思うように取得できず、逆に満足度は下がります。
いまも私は地方在住ですが、この時期、帰省してきた小さい子供を連れた家族が、じいじ、ばあばとの再会を喜び、また別れを惜しむ姿が地上波で映し出されます。多様な働き方が拡がる昨今、過去の遺物、オールドなものになってきているのかもしれません。
とにかく小さい子供を抱えていると、移動時の席の確保が最優先事項になります。いまや新幹線は、普段は自由席が2両、盆暮れ混雑時は全車指定席になっており、子連れ家族には良いことかも知れません。あぶれた乗客が通路に立って乗車することも許容されていますので、急なトイレなどの車内移動に不安が残りますが。。。混雑時に移動することが自体が大イベントであることに変わりないでしょう。
休暇を分散させるのが良いのか、はたまた集中させるのが良いのか、個人レベルから社会経済レベルで、また時と場合によって議論の方向性が変わる、全体最適化が難しく、尽きることのない課題なのでしょうね。
暑中お見舞い申し上げます(2025年7月3日)
(今日の独り言はビジネスと無関係です。)
毎日酷暑が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。私の住む四国・香川県高松市ですが、毎日37~8度が続き、全国の天気予報でトップの座を獲得しています。
ちょうど20年前、九州・熊本市から北海道・札幌市に転勤命令が出て、幼子を抱えて家族で移り住みました。あまりの気温差に体が慣れず、一年ほど体調が悪かった記憶があります。いまでも天気予報で札幌の気温に目が行きますが、最近は西日本より暑い日もあり、30度を超える日が普通になっているようです。私の札幌生活4年間は、クーラーは倉庫にしまったままでしたが、いまだと必須でしょう。
酷暑を乗り切るための夏の楽しみと言えば、クーラーの効いている部屋で呑む冷たいビールですが、一番の楽しみは、いよいよ始まる夏の高校野球です。現在、地方大会が順次開始されており、地元・香川県は、高松商業高校、英明高校といったプロ野球選手を輩出し、甲子園を賑わす強豪校揃いで、地方大会からハイレベルな試合が繰り広げられます。大リーグやプロ野球とは違った面白さ、良さがあります。
皆様におかれましても、酷暑を忘れられるくらいの楽しみを見つけ、何より健康でお過ごしになられますよう、祈念申し上げます。
本日の日経記事から(2025年6月5日)
徳島県、慶応大学が地域課題の解決案 社会人学生が7月提言 徳島 2025年6月5日 7:00 [会員限定記事]
徳島県を舞台に、慶応義塾大学大学院のExecutiveMBA(慶応EMBA)の社会人学生が地域課題に向き合うフィールドワークに取り組んでいる。県が受け入れ、県外への人口流出や過疎地振興などに関し解決案を募る。現地調査や関係者への聞き取り、自身の人脈の活用などにより県への提言を7月末にまとめる。
ーーーーーー
4月以降、ものづくり補助金、省力化投資補助金、持続化補助金、成長加速化補助金とたて続けに公募が始まり、多くのご依頼をいただき、多忙を極めておりました。最近、桜が咲いたと思っていたら、気が付くと、梅雨入りしていました。
補助金といえば、国が補助金の申請者や補助事業に求めていることの一つに地域課題の解決という点があります。公金を投入する訳ですから、収益性が高く、公金を回収できることが大切なのですが、同時に地域課題の解決にもつながれば、高く評価するという仕組みになっています。いまトランプさんでちょっとした話題のアメリカ・ハーバード大学のマイケル・ポーター教授が提唱しているCSV(Creating Shared Value)というビジネスコンセプト、社会的な価値と経済的な価値を同時に生み出すことを目指す経営戦略の考え方と一致しています。
官の視点で考えた施策で行き詰る我が国ですが、あらゆる分野に経営やビジネスの視点を上手く取り入れることで、未来が切り開けるのではないかと思います。補助金の申請案件は、そのアイデア集・宝の山であるように思いますが、審査員が審査したらそれで終わり、やはりまた官の視点に戻っていく。宝の持ち腐れになっていないでしょうか。
記事にある慶應大学EMBA(社会人ビジネススクール)による徳島県での地域課題への提言とその後の徳島県の動きにも注目ですね。
先月の日経記事から(2025年4月2日)
「静かな退職」40〜44歳は最多5.6% 全社員の2倍に 2025年3月21日 2:00 (2025年3月30日 8:00更新) [会員限定記事]
国内でも最低限の仕事しかせず、熱意を失った「静かな退職」状態の人が増えている。働きがいのある会社研究所(東京・港)が企業で働く20〜59歳の男女を対象に調べたところ、2024年12月時点で静かな退職状態の社員は2.8%になり、前回(24年1月)調査より0.4ポイント上昇した。静かな退職者の増加は、職場の連帯感などに悪影響を及ぼしかねない。
ーーーーーー
3月は、事業再構築補助金、省力化投資補助金の申請受付期間が重なり、補助金申請サポートに多数のご依頼をいただき、「独り言」を言う間もないほど、多忙な毎日を過ごしておりました。皆様、お変わりないでしょうか。
新年度が明け、新たな環境で新たなスタートを切られている方もさぞや多いのではないでしょうか。
街を歩いていると、着なれないスーツに身を包んだ若者の集団があちらこちらに。。。明らかに新社会人と分かり、出会いと希望にあふれたその表情にエールを送りたくなります。
しかし、不思議と5月くらいになると、新社会人と普通の社会人の区別が付かなくなります。柔軟性の高さ故か、1カ月するとカメレオンみたいに組織に同化するのでしょう。そして、3か月以内、3年以内に会社から姿を消す。最近では、突然、退職代行業者から電話が。。。なんていうのも笑えない話です。今の人はもっと見切りが早いのかも知れません。例えば3日、3時間、3分とか。
何が原因なのでしょうか。先日、日本人は共感性が低いという研究結果が発表されていましたが、これが思い浮かびました。
知らず知らずのうちに、同調圧力がかかっていないでしょうか。あるいは、個に対する無関心さを感じさせていないでしょうか。個性を尊重する教育を受けてきた世代に、個性を押し殺すことを要求されることや軽視されることほど、苦痛なことはありません。厳しいようですが、変わらなければならないのは、受け入れる組織側かも知れません。昨今の就活生は安定志向、などと言われていますが、親に近い就職氷河期世代の不遇をさんざん聞かされているからでしょう。しかし、折角、安定した組織に就職をしても、耐えきれず&他がいくらでもあるというタカのくくりで早期退職する、そんなジレンマに陥っているのだと思います。
逆にこの記事にあるように、個性を押し殺すことを是とし、組織に寄生することに徹している人も多くなっています。もとより大企業や公務員の世界はそれなりに多いのでしょうが、人手不足の中小企業に拡がっていないか不安です。表に出てきづらい問題ですが、ボディブローのように効いてくる問題なのでしょう。「静かな退職」というのが、流行語にならなければいいのですが。
マイナス金利の解除で好業績を上げる銀行を中心に、初任給を大幅に上げる企業が増えていますが、本当にそれが優秀な人材獲得と定着につながるでしょうか。それより、本当の意味で、社員一人一人に目を向け、それぞれの個性を受け入れ、活かそうとする組織になれるかどうかが大切だと思います。これからの時代の強い組織というのは、そういったものに違いないと思います。
今週の日経から(2025年2月24日)
〈NEO-COMPANY それでも進む〉冒険続けよう、逆境こそ活力 2050年の社長に託す言葉 2025年2月23日 2:00 [会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO86923450T20C25A2MM8000/
2050年、企業のあり方はどうなっているだろうか。日本の人口減少とグローバルサウスの成長、人工知能(AI)の進化、働き方の変化。会社経営は今以上に困難かつ挑戦的になるはずだ。25年後の社長に向けて託したい言葉を様々な経営者に聞いてみた。(総合5面に主な経営者のメッセージ)「かっこいい店を作るなよ。俺たちは大衆芸能だ」
ーーーーーー
25年先を見越して企業の舵取りをする社長たちのメッセージを見ていると、困難、挑戦、そしてそれらを冒険のごとく楽しんでいるかのようです。冒険と言えば、小中学生の頃にワクワクしながら観ていたインディジョーンズなのですが、一寸先は闇、困難だらけの中にあって挑戦と冒険を楽しむ、何かのエンターテインメントでも観ているような感覚に陥ります。どんな困難さえも楽しんでしまう極度の「前向きさ」、逞しい「想像力」、どこまでも失われることのない「自信」。これが充実したビジネスシーンと人生を歩むビジネスパーソンの共通項なのかもしれません。
そして、記事の中に、人生100年時代では、2週分の人生を歩めるとあります。
ビジネスで言えば、40代から50代のいわば折り返し地点で、それまでのファーストキャリアに終止符を打ち、学び直しをして生まれ変わり、起業して自分のやりたいように仕事をするなど、はるかに価値のあるセカンドキャリアを歩める&楽しめる、そんな素敵なことができるようになったのだと思います。
私自身もそれに近しいものがあります。その素敵さを噛みしめながら日々過ごしているように思えます。「幸福とは義務である」という言葉がありますが、まさにその通りだと思います。「人生一度きりなんだから」という言葉が一般的に使われますが、それに負けじと「人生一度きりではないんだから」という言葉を流行らせていこうと思います。
今週の日経から(2025年2月16日)
安住の家なき氷河期世代 所有率低下、40代は6割切る 物価高騰が追い打ち 2025年2月16日 2:00 [会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO86765620W5A210C2MM8000/
40~50代の持ち家率が急低下している。国の最新の調査では全世代平均は横ばいだが、30年前と比べ10ポイント前後も下がった。このまま高齢期に近づく人が多い。今のこの年代は就職氷河期世代(総合2面きょうのことば)といわれ、就職難に見舞われた。現在も経済的な苦境は続いており、老後の年金も多くを望めなければ賃貸に住むこともままならない。「安住の家」を求めてさまよい続けることになる。
ーーーーーー
何を隠そう、私も就職氷河期世代、賃貸暮らしの一人です。
私の場合、社会人スタートから長く転勤族だったため、社宅暮らしが長く、転職後は転勤族ではなくなりましたが、いきなり家を買うハードルの高さや、子供も小さく緊急性を感じないため、賃貸暮らしを選択し、そのままといった感じです。特に劣等感や不安感などは感じません。
江戸時代から、日本人は長屋の借りぐらしがスタンダードだったのが、戦後、高度成長期には、欧米列国のような暮らし、家や車を買う「ジャパニーズ・ドリーム」が一億総中流社会であまた実現され、ニュー・スタンダードになりました。しかし、昨今、家や車に興味のない若年世代が消費のメインを占めるようになり、オールド・スタンダードになりつつあるのでしょう。
個人的には、見栄や世間体で高額なものを所有すれば、満足度以上にストレスが増えて、逆に幸福度は下がる、そして家を所有していないからこそ、リスクに強い家計になっている、という点もあると思います。何か起きた時に足かせになりそうなものは極力持たない、変化の激しい世の中を生き抜いていくためには、大事なことだと思います。
これは、企業経営にも通じる点があるかも知れませんね。
今週の日経記事から(2025年2月10日)
日鉄ディール、望み残す 玉虫色の「投資で合意」 2025年2月8日 21:48 [会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC075I50X00C25A2000000/
日本製鉄の米USスチール買収交渉が再び動き出す可能性がでてきた。トランプ米大統領は7日、「買収ではなく、投資で合意した」と表明した。今後、米政府と協議することになるが、「投資」が何を示すかは明らかになっていない。玉虫色の内容といえ、交渉の先行きは依然として不透明だ。トランプ氏は日米首脳会談後の記者会見で「買収」は何度も否定し、「投資」だと話した。「投資は大好きだ」としたが、その真意は不明だ。
ーーーーーー
診断士、経営者として活動をしていると、日々色んな仕事の話が舞い込んできます。本当にwin-winと思える話から、随分とご都合のいい話まで。残念ながら、前者寄りは少なく、後者寄りは多いです。買収ならぬ搾取、弱い所に付けこみ、他人の知識、知恵、労働で、楽して儲けようというのは、いい気持ちになれません。ただこれは、事業主、経営者をやっていると、日常茶飯事です。
トランプさんも、ビジネスパーソンとして、こういったことを星の数ほど経験してきたのでしょう。その中で「君に投資する(かけてみる)よ」という言葉を言われることも、言うことも、両方あったと思いますが、そこでは、将来性が目利きされ、信頼感ある対等な関係性の中から出てくる、最高の賛辞なんだろうと思います。一介のビジネスパーソンとして、その言葉に大量のアドレナリンが出るのでしょう。
投資と言えば、一昔前は、面倒見の良い人・企業が多かったと思います。世の中に余裕があったからでしょうか。
目先の利益を捨ててでも、組織レベルでは新人へと、業界レベルでは新興企業へと、思い切りよく仕事を任せ、真っ当なフィーと労いの言葉で報い、一人前に育んでいくことが、まさに投資であり、組織や業界全体のレベル底上げにつながっていたのでしょう。
投資の心意気とセンスのあるビジネスパーソン、企業が多いビジネスフィールドであって欲しいですね。
今週の日経記事から(2025年1月30日)
DeepSeekの衝撃 中国AIが変えたゲームのルール 2025年1月28日 11:00 [会員限定記事]
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOGM27BNR0X20C25A1000000/
中国の生成AI(人工知能)スタートアップ、DeepSeek(ディープシーク)が米オープンAIの「Chat(チャット)GPT」を超えるといわれる新モデルを発表した。圧倒的な低コストを主張する同モデルの登場でAI業界のゲームのルールは一変した。激化する米中AI戦争はこの先の世界の形すら変えようとしている。
ーーーーーー
皆さん、生成AIを活用してますか?
私は、昨年夏に生成AI「Chat-GPT」を使い始め、いまでは日常生活、仕事共に、無くてはならない存在になりつつあります。
かつての「読み・書き・そろばん」は、いまや「数理・データサイエンス・AI」と言われています。まだ使いこなせている、と言えるほどではありませんが、生成AIは、スマホをはじめ、いろんなものに組み込まれており、自覚はなくてもかなり使っている、ということになるのかも知れませんが。。。
今回、中国の新興企業ディープシーク社が生み出した生成AIアプリが、米国企業のそれと比べてコストが10分の1、性能も上回っていると言われ、全米アプリランキングでもトップになるなど、世界を震撼させています。米中間では、貿易戦争だけでなくAI戦争も熾烈を極めています。
日本でも国産AIの開発が進んでいますが、既に追い付くのは到底難しそうな状況です。近い将来、AIが変える世界で、日本がどれだけの存在感を示せるのか。世界に誇れる「何か」を作らなければ、本当に置いて行かれてしまいそうです。
日本の中小企業の持つ、自由で柔軟な発想力に未来が託されていると思います。
年始ご挨拶・中小企業庁長官年頭所感を受けて(2025年1月3日)
新年あけましておめでとうございます。弊社の中心的活動エリアである四国、近畿地方では、年末年始、おおむね好天に恵まれ、穏やかな年越し及び年明けとなっています。今年一年、皆様にとって、穏やかで実りある年となりますよう、心より祈念いたします。
さて、毎年元日に中小企業庁ホームページで発表される「中小企業庁長官年頭所感」を見ますと、その年の補助金を中心とした中小企業政策の方向性や狙いが見えてきます。これをチェックして、念頭に置いているかどうかで、政策活用度(補助金採択)に大きな差が生まれると言っても過言ではないでしょう。自社事業の方向性を考えるうえでも、大いに参考になります。
今年元旦の所感では、「取引適正化の推進(価格転嫁余地拡大)」「生産性向上支援(省力化投資等による物価高騰・人手不足克服)」「成長投資支援(100億企業創出)」の3つの方向性が示されており、それらは「賃上げ原資の確保」が目的とされています。それによりデフレを脱却し、消費と投資の好循環を回す、というのが大筋の内容となっています。
【令和7年元旦中小企業庁長官年頭所感】https://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/nentouShokan/2025year.html
先週の日経記事から(2024年12月29日)
吉野家HD、京都のラーメン店「キラメキノトリ」買収 2024年12月26日 17:26
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC267UP0W14A221C2000000/
吉野家ホールディングス(HD)は26日、京都府内などで「キラメキノトリ」などのラーメン店を展開するキラメキノ未来(京都市)を買収すると発表した。取得額は非公表。吉野家HDはラーメンを牛丼やうどんに次ぐ成長の柱と位置付けており、買収をてこにラーメン事業の拡大につなげる。
(中略)
吉野家HDはラーメン店を牛丼店とうどん店に次ぐ収益源に育てる方針を掲げており、子会社のウィズリンク(広島市)やせたが屋(東京・世田谷)を通じて国内外でラーメン店の展開を加速している。5月にはラーメン店向けに麺やスープなどの製造を手がける宝産業(京都市)を買収した。
ーーーーーー
先日、東京でラーメンを食べる機会がありましたが、1杯1,500円の値段に驚きました。私の中では1杯7~800円のイメージでしたが、完全にゲームチェンジでしょうか。資材、人件費高騰によるコストプッシュであると推測されますが、インバウンドの多い東京などの都市部であれば、その値段でも十分な需要があるのかも知れませんが、地方部では厳しいかも知れません。
ラーメン店に限らず、このところの資材、人件費高騰から、廃業を指向する飲食店が増えてきており、飲食業界ではM&Aが一層進むとされています。売手にとっては経営者の悩みどころである雇用維持策や転廃業の資金源になり、買手にとってはスピードある成長機会となり、Win-Winの関係のうえに成り立つM&Aが増えることは大歓迎かも知れません。ちなみに、記事にある吉野家はラーメン事業を世界戦略に位置づけていて、今回のM&Aもその道筋にあると言われています。
飲食業界に限った話ではなく、M&Aは何でも「身売り」と言われた時代もありましたが、以前ほどネガティブな印象はなくなってきており、身近で耳にすることも多くなりました。国も経済対策として事業承継・M&Aに力を入れていて、支援策も充実してきたこともあり、自社事業の将来を考える経営者にとっては、M&Aはますます有力な選択肢になってきているのでしょう。
今日の日経記事から(2024年12月14日)
<ピックアップ記事>
2024年版「共働き子育てしやすい街ランキング」 総合編1位は神戸市
https://www.nikkeibp.co.jp/atcl/newsrelease/corp/20241213_2/
2024年12月13日
働く女性向けウェブメディア「日経クロスウーマン」(発行:日経BP)と日本経済新聞社は「自治体の子育て支援制度に関する調査」を実施。2024年版「共働き子育てしやすい街ランキング」をまとめた。総合編1位は神戸市(23年は総合編4位)。15年の調査開始から初めて、西日本の自治体が1位を獲得した。結果の詳細は日経クロスウーマンと日本経済新聞にて発表した。
ーーーーーー
ビジネスを取り巻く外部環境の中でも、人口増加というのは、ビジネスにとって一番の「機会」なのかもしれません。
日本の少子高齢化が言われて久しいですが、まさに今から、数値上の人口減少が始まり、急速に高齢者比率が高まっていく局面となります。
危機感の強い自治体は、早い段階から先手、先手で施策を行い、実効性を見極めながら試行錯誤し、移住増加などの「目に見える結果」に繋げてきたのだと思います。逆に「アリバイ工作」的な施策を繰り返し、予算を出し惜しみしてきた自治体とは、差が開く一方になると思います。「自治体を選ぶ時代」がきているのかもしれません。
中小企業を支援する立場からこの記事を見て思うのは、事業所(工場、店舗など)の進出地域を検討する企業にとって、子育て支援に注力する自治体地域というのは、有力候補になりうるのではないか、ということです。もちろん、それ以外にもいろいろな要素がありますので、一概には言えないとは思います。
しかし、女性の働き手増加、商圏における経済規模の拡大など、このご時世あまり吹かれることが少ない「追い風」を背中に受けながらビジネス展開ができれば、生き残りに有利な道が開けるのではないかと思います。
今日の日経記事から(2024年11月26日)
<ピックアップ記事>
https://www.nikkei.com/article/DGKKZO85026900V21C24A1TB2000/
〈小さくても勝てる〉中小、趣味休暇で人材集め アユ釣りやポケモン、有休と別枠 後ろめたさ解消へ知恵(2024年11月26日 2:00 [会員限定記事])
プライベートを重んじる働き方改革の一環で、会社が取得目的を自由に決められる「趣味休暇」に着目する中小企業が増えている。アユ釣りや「ポケモン」大会を理由に休みを認める例がある。法的には導入する義務のない特別休暇を設けて社員に寄り添う姿勢を示し、採用につなげる狙い。専門家は「制度作りで終わらず取得率を上げることが大切」と指摘する。
ーーーーーー
中小企業を中心に高卒人材獲得が熾烈を極めています。
私は団塊ジュニアで、大学生と高校生の子供がいますが、団塊ジュニアの子供、つまり15歳から25歳までの年齢層というのが、若年層の中でも人口が多くなっており、それより下の年齢層の人口は減る一方となっているため、特に地方では、いまからしばらくの間が人材獲得の大事な時期なのかもしれません。
近頃の若年層が一番気にする労働条件とは「休暇」だそうです。私の頃は「給料」のところばかり見ていたものですが、時代は完全に変わったと感じます。いくら初任給を上げても人材が集まらない、そんな経験をしている経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。<ピックアップ記事>にあるようなユニークな特別休暇制度を設けてみるのも、解決策の一つになるのかも知れません。
先週の日経記事から(2024年11月24日)
<ピックアップ記事>
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOTG2580L0V21C24A0000000/
日本企業、欧米より「現金稼ぐ力」軽視 10年横ばい(2024年11月22日 11:00 [会員限定記事])
日本企業の現金を稼ぐ力が伸び悩んでいる。主要な上場約400社で売上高と本業で稼いだキャッシュの比率を比べたところ、2023年度で10.4%と過去10年間、横ばい圏が続く。売上高や利益の額を追い求める経営から抜け出せておらず、在庫の増加も重荷だ。米欧勢との差は大きく、成長投資で後れをとりかねない。
ーーーーーー
<ピックアップ記事>を見てふと思い出しました。
先週、東大阪で開催された中小企業向けのセミナーに参加した際、地元中小企業の参加者の方から「売上や利益は気にしても、キャッシュフローを気にしていない中小企業が多い。売上が伸びているのに、資金繰りが厳しくなるといったことが起きるが、原因がはっきりせず困っている中小企業は多い。」といったお話を伺いました。
建設業を中心に、黒字倒産が増加傾向にあると言われており、資金繰りに悩みを抱える中小企業も多くなってきたと感じます。不確実性の高い時代、経営の安定や成長に向けた原資を確保するために、キャッシュフローにもしっかりと目を向けていく必要があるのかも知れません。
OSAKAビジネスフェア2024に行ってきました!(2024年11月22日)
2024年11月22日(金)マイドームおおさかで開催された「OSAKAビジネスフェア2024」(主催:大阪信用保証協会)に行ってきました。
https://event.osaka-bizfair.net/
2階、3階と2フロアに分かれており、大阪をはじめとした近畿を中心に全国の中小企業が約150社出展しており、商談獲得に向けて大変な熱気でした。
各社がアピールする商材も、自社の開発力・技術力を存分に生かして、アフターコロナでの需要増加を捉えたもの、自然災害の増加を踏まえた防災関連のもの、などなど、つい唸ってしまうものが多くありました。
このような商材に触れているうち、「刻々と変化する外部環境(特に社会課題)に目を向けつづけるとともに、開発力・技術力を高めつづけること」が、今日の企業経営にとって非常に重要になってきている、と改めて感じました。